Artist: Cola Ren
Title: Mekong Ballad
Cat#: ARTPL-246
Format: CD / Digital
※日本独自CD化
※ボーナス・リミックス・トラック3曲収録
※解説付き
Release Date: 2025.11.05
Price(CD): 2,000 yen + tax
広州発、音と詩情で水を描く若きプロデューサーCOLA RENが名門Human Pitchとサインして新作EP『Mekong Ballad』を11/5リリース決定!自身の歌声を初披露!ボーナス・リミックス・トラック3曲を加えアルバム仕様で日本独自CD化!
共にThe Lot RadioでレジデントDJも務めてきたSimisea(レーベルSLINKも運営)とTristan Arp(UKのWisdom Teethなどから作品をリリースし、Asa Toneのメンバーでもある)が主宰するアンビエント〜実験音楽の最前線を提示し、SalamandaやLe Fritなどをリリースしてきた優良レーベルHuman Pitchが、新たに中国・広州を拠点とするプロデューサー/DJのCOLA RENとサイン。
COLA RENは、都市と自然、記憶と夢のあわいを繊細なサウンドスケープで描く若き音楽家であり、これまでフィールド・レコーディングやエレクトロニクスを駆使した詩的なインストゥルメンタル作品で注目を集めてきた。
そんな彼女が、自身の声を初めてフィーチャーした新作『Mekong Ballad』で、表現の新たな地平を切り拓く。
本作には、川の息吹や熱帯の空気の重みから着想を得た5つのアンビエント・トラックを収録。
楽曲は流れる水面に映る光の反射のように漂い、溶け、屈折し、また戻ってくる。落ちた果実、ささやく水流、河口に差す月光の霞――記憶の断片が浮かび上がるこの作品は、水への瞑想であると同時に、無重力感や居場所を探す旅のようでもある。
タイトル曲ではCOLA REN自身が歌声を披露し、中国語の歌詞は J-Fever(小老虎)が手掛けている。特徴的なアンビエント・サウンドに人間の声が加わることで、より深みのある表現が生まれている。
また、中国フリージャズ・シーンのスター tga(サックス)、タイの即興演奏家 rrrrrm(トランペット)が参加し、楽曲に呼吸と共鳴の豊かな流れをもたらす。これらの演奏によって、川や記憶、夢が交錯するCOLA RENの流動的な音世界に、有機的で人間らしい脈動が加わっている。
さらに、日本のみでリリースとなるCD盤にはMong Tong、Guohan、Wu Zhuolingによるリミックス3種を収録し、オリジナルとリミックスを併せた、フルレングスのフィジカル・リリースとなる。
Tracklist:
1. Mekong Ballad
2. Be Water
3. Fallen Papaya
4. Ripples
5. A Sudden Wind
CD edition:
6. Mekong Ballad (Guohan’s Dub)
7. Mekong Ballad (Mong Tong Remix)
8. Mekong Ballad (Wu Zhuoling Remix)
Credits:
Composed and produced by Cola Ren
Lyrics on track 1 written by 小老虎 J-Fever
Tenor saxophone on track 1 by tga
Trumpet on track 2 by rrrrrm
Artwork by Lanxin Zhao
Calligraphy on CD by Popol Wu
composed and produced by COLA REN
Mastered by Tristan Arp





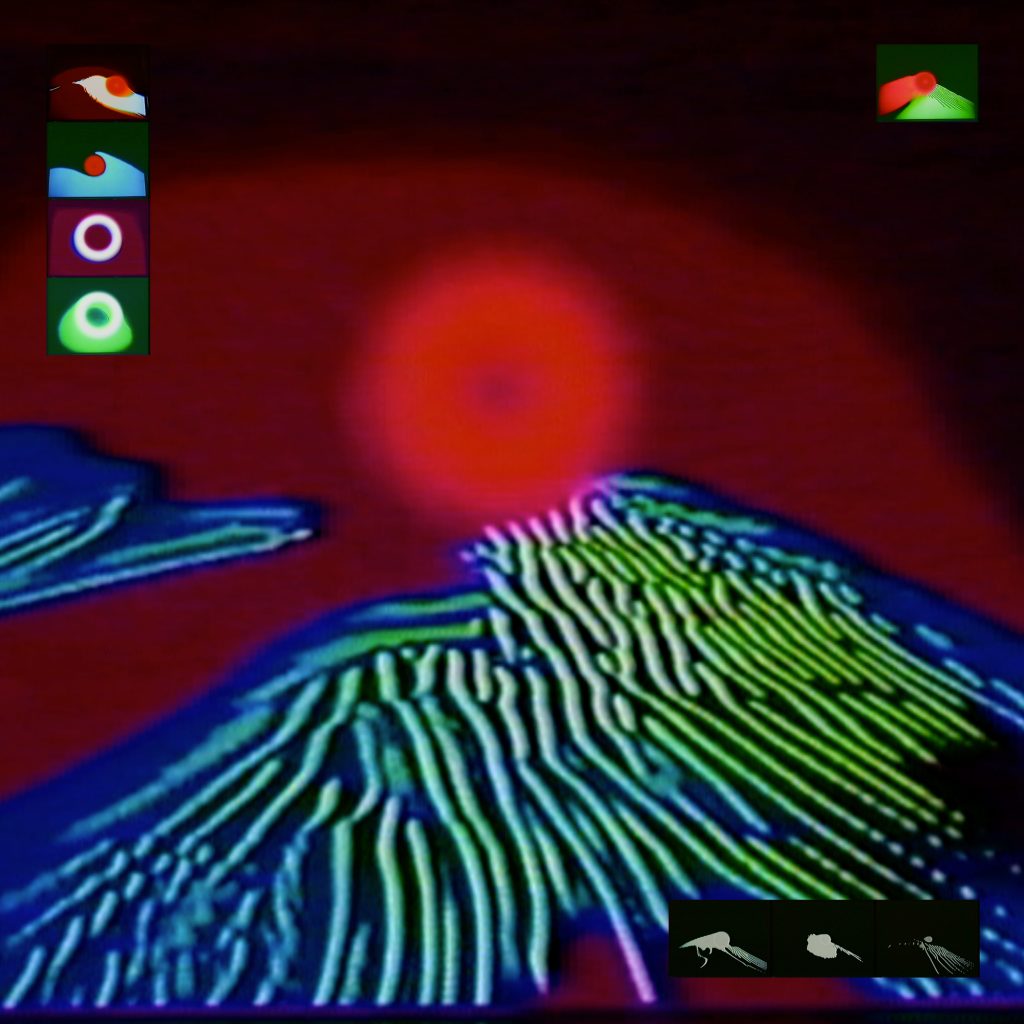
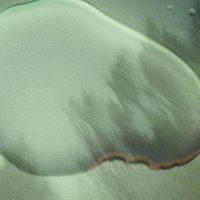
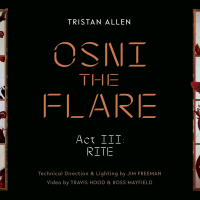




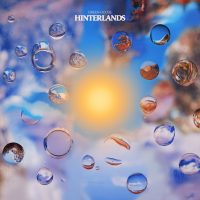


![JULIANNA BARWICK & MARY LATTIMORE “Tragic Magic” [ARTPL-250] JULIANNA BARWICK & MARY LATTIMORE “Tragic Magic” [ARTPL-250]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2026/01/ARTPL-250-200x200.jpg)
![DAPHNI “Butterfly” [ARTPL-247] DAPHNI “Butterfly” [ARTPL-247]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/Daphni-2026-FINAL-3000-200x200.jpg)
![DAVID MOORE “Graze the Bell” [ARTPL-249] DAVID MOORE “Graze the Bell” [ARTPL-249]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/RVNGNL132_1500px-200x200.png)
![AREA 3 “View” [ARTPL-245] AREA 3 “View” [ARTPL-245]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/12/ARTPL-245-200x200.jpg)
![FABIANO DO NASCIMENTO “Cavejaz” [ARTPL-248] FABIANO DO NASCIMENTO “Cavejaz” [ARTPL-248]](https://www.artuniongroup.co.jp/plancha/top/wp-content/uploads/2025/11/Cavejaz-Packshot-A-200x200.jpg)